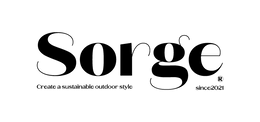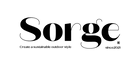自由を運ぶ車、ヴァナゴンT3──“便利さ”よりも“ライフスタイル”を選ぶあなたへ
都会の喧騒に飲み込まれ、時間に追われる日々の中で、ふと「もう少しゆっくり生きたい」と感じたことはありませんか。
Sorge代表の浅山がバンライフの相棒に選んだ車が「フォルクスワーゲン・ヴァナゴンT3」です。

1980年代にドイツで生まれたこのバンは、単なる移動手段ではなく、“生き方そのもの”を乗せて走る存在であり、旅と暮らしのあいだを自由に行き来しながら、「自分のペースで生きる」という豊かさを思い出させてくれる車でもあります。
そこで今回はこの「フォルクスワーゲン・ヴァナゴンT3」をご紹介したいと思います。
ヴァナゴンT3とはどんな車か
フォルクスワーゲン・ヴァナゴンT3は、1979年に登場した「タイプ2(ワーゲンバス)」の後継モデルです。
丸みを帯びた先代に比べて、T3は角張ったスクエアデザインが印象的で、どこか工業的で無骨な佇まいの中に温もりと親しみを感じさせるバランスがあります。
1980年代当時、ヴァナゴンは単なるファミリーカーや商用車として生まれました。しかし、エンジンを後部に搭載する独自の構造により、車内が驚くほど広く、フラットな空間を確保することに成功しました。そしてこの“居住性の高さ”が、後に「走る家」「旅するリビング」として愛されるきっかけになります。
やがてウエストファリア社などが手掛けたキャンピング仕様(ベッド・収納・キッチン付き)が登場し、ヴァナゴンは“暮らせる車”として進化しました。
そして人気が爆発したのは生産終了後、2000年代に入りスローライフやバンライフが注目される中で、そのアナログな構造と味わいが再評価され始めてからでした。
その結果、今では世界中で憧れの存在となっています。
ヴァナゴンが象徴する“自由”と“生き方の哲学”

ヴァナゴンは、ただ古いバンというだけではありません。それは「便利さやスピードでは測れない豊かさ」を象徴する存在でもあります。
ヒッピーカルチャーの自由精神を受け継ぎながら、時代の変化とともに“心の自由”へと意味を広げていきました。
ヒッピーカルチャーから受け継がれた「自由の原型」
ヴァナゴンのルーツにあるのは、1950〜70年代の「ワーゲンバス(タイプ2)」です。この車はヒッピーたちに愛され、戦争や物質主義に背を向けた“ピース&ラブ”の象徴でした。
ヴァナゴンはその思想を現代的に受け継ぎ、より現実的で穏やかな「暮らしの自由」へと進化しました。
“世界を変える”ではなく、“自分の世界を見つめ直す”。
その静かな自由が、今の時代にこそ響いているのです。
“逃げる自由”から“戻る自由”へ──心の回帰としてのヴァナゴン
現代のバンライファーたちは、ヴァナゴンに“逃避”ではなく“回帰”の自由を重ねています。仕事や情報に追われる社会から一歩離れて、「本来の自分」に戻るための場所こそが、ヴァナゴンの中の時間です。
不便だからこそ、時間の流れがゆっくりになる。ハンドルを握りながら風の音を聴く時間が、心のリズムを整えてくれることが人気の秘密の一つでもあります。
不完全だからこそ美しい、“未完成の自由”

ヴァナゴンは最新の車のように静かでも速くもありません。しかし、その「手間のかかる構造」こそが、人を惹きつけます。
修理しながら乗る。手をかけながら長く付き合う。その過程で生まれる愛着は、まるで人間関係のようであり、Sorgeの哲学とも合致する点でもあります。
便利さを手にした現代において、“不完全さを愛する自由”こそが、最も贅沢なのかもしれませんね。
“足るを知る”という豊かさ──便利さよりも確かさを
ヴァナゴンの中には、必要なものしかありません。それでも不思議と不便さを感じないのは、そこに「心の余白」があるからなのかもしれません。
少ないモノで満たされる体験は、心理学的にも「自律性」と「満足感」を高めるとされています。つまり、ヴァナゴンで過ごす時間は“足るを知る豊かさ”を思い出す旅でもあるわけです。
侘び寂びとヴァナゴン──日本人が共鳴する「静かな美」
日本人がヴァナゴンに惹かれるのは、どこかに“侘び寂び”の美学を感じさせるからなのかもしれません。錆びたボディ、使い込まれた木製の内装、わずかに軋むドア音。そのひとつひとつが「時間の痕跡」として美しいですよね。
新しくなくても、速くなくても、そこに“人の手の温度”がある。それは、日本人が古くから大切にしてきた「手入れの文化」と深くつながっているかのようです。
バンライフにおけるヴァナゴンの立ち位置

“バンライフ”という言葉が広がる中で、ヴァナゴンは新しい世代にとっても特別な存在になりました。
それはただのクラシックバンではなく、「生き方を問うための車」であり、効率やスピードを求める社会の中で、“本当の自由とは何か”を静かに教えてくれる相棒でもあるのです。
バンライフ文化の源流──自由を旅に変えた車
バンライフの起点にあるのは、「車の中で暮らす」ライフスタイルへの憧れです。その文化を作ったのが、他でもないヴァナゴンなのです。
ベッドやテーブルを備えた車内は、まるで“動く家”であり、どこにいても自分の空間があるという安心感が、人々に「旅する暮らし」の魅力を教えてくれたわけです。
“所有する”から“動ける”へ──新しい自由のかたち
かつて自由は「何を持つか」で測られていました。しかし現代では、「どこへ行けるか」「どんな時間を過ごせるか」が自由の尺度に成り代わっています。
ヴァナゴンは、“所有の自由”から“移動する自由”へのシフトを体現しています。それは、固定観念や場所から自分を解放する、生き方・ライフスタイルそのものの象徴です。
なぜ日本のバンライファーはヴァナゴンに惹かれるのか
日本のバンライファーがヴァナゴンを愛する理由の一つは、ヴァナゴンと過ごすライフスタイルが“心の居場所”になっているからなのかもしれません。

都市のスピードに合わせることをやめ、自然のリズムに身を委ねる。その小さな車内で飲むコーヒー一杯が、何よりの贅沢に感じられる。旅先での出会いや体験こそが、お金では手に入れることができない、真の人生を豊かにしてくれるのかもしれません。
つまりヴァナゴンとのバンライフは、今の生活に対する違和感から解放されて「心と空間の自由を実感」するための最適解の一つなのです。
最後に…
ヴァナゴンT3は、快適に・素早く・効率的に・より遠くへ行くための車ではありません。
しかしその歴史や思想やデザインでしか実現することのできない、豊かさや満足感は必ず存在しています。そしてそれはSorgeが大切にしている哲学と一致しています。
ぜひSorge代表の浅山とヴァナゴンT3とのバンライフの様子を通じて、何かを感じ取っていただき、ご自身のライフスタイルや仕事の取組みを見直すきっかけにしてもらえたら嬉しいです。
追伸
バンライフの様子をお届けしているInstagramはコチラ