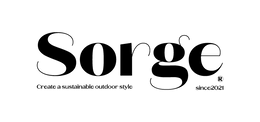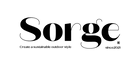鉄製フライパンの魅力と正しい使い方|一生モノに育てるための入門ガイド
近年のアウトドアシーンやキャンプ料理で注目を集めている「鉄製フライパン」。
実はその魅力は屋外だけでなく、毎日の家庭料理にもぴったりで、プロの料理人から料理好きな一般ユーザーまで、幅広く支持されています。

高温調理に強く、食材本来の旨みを引き出してくれる鉄フライパンは、まさに“一生モノ”の調理道具。とはいえ、「焦げやすそう」「お手入れが大変そう」といった不安から、なかなか手を出せずにいる方も多いかもしれません。
この記事では、そんな鉄製フライパンの魅力や種類の違い、使い方のコツや注意点などを初心者にもわかりやすく解説しますので、愛着が生まれる一品を選ぶ際の参考にしてください。
まず知っておきたい!鉄製フライパンの3つの特徴
香ばしい焼き目と高温調理の力
鉄製フライパンの最大の魅力は、「高温調理」に強いという点です。熱がしっかり伝わりやすく、なおかつ蓄熱性が高いため、食材を入れても温度が下がりにくいのが特徴です。これにより、ステーキや餃子、野菜炒めなどで理想的な焼き目をつけやすく、素材の旨みを閉じ込めた香ばしい仕上がりが実現します。
とくに、香りや食感を重視する料理ではその実力を発揮します。料理の腕前が上がったように感じられるのも、鉄フライパンならではの効果です。「炒める」「焼く」に強いという特性は、日々の家庭料理にもアウトドアでも重宝される理由の一つです。
丈夫で長持ち、一生モノの道具になる
鉄製フライパンは、適切な手入れをすれば10年、20年と長く使える「一生モノの調理道具」です。テフロン加工などと違って、コーティングが剥がれることがないため、買い替えの必要がほとんどなく、長期的に見るととても経済的です。むしろ、使い込むほどに表面が油となじみ、焦げつきにくくなるという“育つ”特徴があります。
さらに、経年変化でツヤが増していくのも魅力の一つ。自分の手で道具を育てる感覚は、愛着を深める要素になります。料理が好きな方はもちろん、ものを大切に長く使いたいという方にもぴったりです。
自然な鉄分補給で、体にもやさしい
鉄製フライパンで調理をすると、ごく微量ではありますが、食材に鉄分が移ることがわかっています。特に水分や酸を含む料理(トマトや酢を使った炒め物など)では、より多くの鉄分が溶け出しやすいと言われています。この自然な形での鉄分摂取は、サプリメントに頼らずとも不足しがちなミネラルを補える点で注目されています。
特に鉄分不足になりやすい女性や成長期のお子さまにとっては、嬉しい副次的効果といえるでしょう。「料理をしながら、ちょっと体にもいいことをしている」という満足感が得られるのも、鉄フライパンを使う魅力のひとつです。
鉄製フライパンの種類と加工の違い
テフロン・フッ素加工との違いとは?

テフロン(フッ素樹脂)加工のフライパンは、焦げつきにくく、手入れも簡単という点から長年家庭で親しまれてきました。しかし、その加工は経年劣化により剥がれてしまい、数年ごとの買い替えが前提になることが多いのが実情です。一方で鉄製フライパンは、適切に扱えば一生使えるという耐久性が大きな魅力です。
また、調理の温度帯も異なります。テフロン加工は高温に弱いため強火での使用が制限されますが、鉄製フライパンは高温に強く、炒め物やステーキなどを美味しく仕上げるのに最適です。扱いに慣れるまでは少し手間がかかるものの、その分、料理そのものを楽しむ感覚が得られるのも鉄の魅力です。
鉄フライパンにもいろいろある?製法の違い
ひと口に鉄製フライパンといっても、製法によって使い心地や特性が異なります。主な製法は「打ち出し」「鋳鉄」「プレス」の3種類。打ち出し製法は、鉄板を何度も叩いて成形する職人技が光るタイプで、熱伝導が良く軽量な点が特長です。鋳鉄製は分厚く蓄熱性に優れ、じっくりと熱を通す調理に適しています。
プレス加工は比較的手頃な価格帯で手に入りやすく、量産性に優れています。どの製法が合うかは、使うシーンや求める調理性能によって変わります。初心者であれば扱いやすい打ち出しやプレス加工、キャンプ好きなら無骨な鋳鉄というように、自分のライフスタイルに合わせた選び方がポイントです。
クリア焼き付け塗装とハードテンパー加工とは?
最近の鉄製フライパンは、「重くて手入れが大変」といった従来のイメージを覆すように、扱いやすさが進化しています。ここでは主な加工である「クリア焼き付け塗装」と「ハードテンパー加工」という2つの加工方法の違いをお伝えします。
まずクリア焼き付け塗装は、鉄の表面に薄い透明なコーティングを施すことで、サビを防ぎつつ見た目の美しさもキープできるのが特徴です。製品によっては購入後すぐに使えるものもありますが、基本的には軽いシーズニング(油をなじませて加熱する処理)を行うことが推奨されています。
一方、ハードテンパー加工は、鉄の表面を高温で焼き締めて酸化皮膜をつくることで、自然な油なじみとサビへの強さを両立した加工です。こちらはシーズニング済みで出荷されることが多く、初心者でも比較的スムーズに使い始められるのが魅力です。

※Sorge×藤田金属の無骨シェラパンはハードテンパー加工を施しています
ちなみにシーズニングとは、鉄製フライパンの表面に油の膜をつくることで、焦げつきを防ぎ、サビにくくする“慣らし作業”のことです。手間がかかりそうに見えて、実際は数分で終わる簡単なステップです。
どちらの加工も、「鉄は難しそう」と感じていた人にこそ試してほしい、現代的な工夫が詰まったアプローチです。
実際どう?鉄製フライパンのメリットとデメリット
メリット|美味しさ・健康・長持ちの三拍子
鉄製フライパンの最大のメリットは、料理が格段に美味しくなるという点です。高温での調理が得意なため、表面をパリッと香ばしく仕上げることができ、ステーキや炒め物などに最適。火加減をコントロールすることで、素材の旨みを最大限に引き出せるのは、まさに鉄の特権です。
加えて、鉄分が微量ながら自然に食材へ移るため、日常の料理で無理なく鉄分を補給できるという健康面での効果もあります。そして何より、正しく使えば10年、20年と長く付き合えるのが魅力。買い替えの必要が少なく、使うほどに油がなじみ、育てる喜びを感じられるのが鉄製フライパンの真価です。
デメリット|重さや焦げ付きには慣れが必要
一方で、鉄製フライパンには注意すべき点もあります。まず第一に「重い」という声が多く、特に直径が大きくなるほど取り回しが大変になります。また、調理前の予熱が不十分だと食材がくっつきやすく、初心者は焦げ付きに悩むこともあります。慣れるまでには多少のコツと経験が必要です。

※Sorge×藤田金属の無骨シェラパンは職人の技で軽量化に成功しています
さらに、使い終わった後に洗剤を使わずに洗う、洗った後は水気を飛ばして油を塗るなど、お手入れにも一手間がかかります。日常の家事に追われていると「少し面倒…」と感じるかもしれません。ただし、これらのポイントを習慣化できれば、手間以上の満足感と調理の楽しさを味わえるのも事実です。
鉄製フライパンを育てて長く使うために
はじめにやるべき“焼き慣らし(シーズニング)”
鉄製フライパンを購入したら、まず最初に行いたいのが「焼き慣らし(シーズニング)」です。これは、表面に薄く油の皮膜をつくり、焦げつきを防ぐと同時に、サビにくくするための大切な工程です。最近では出荷時にシーズニング済みの商品も増えていますが、未処理のものは必ず行いましょう。
シーズニングは決して難しい作業ではありません。油を入れて中火〜強火で煙が出るまで熱し、その後キッチンペーパーで油を全体になじませるという流れを数回繰り返すだけです。この一手間をかけることで、鉄フライパンは一気に“育ち始める”準備が整います。
日々のお手入れ|洗剤は基本NG?乾かし方と油の塗り方
鉄製フライパンは、洗剤でゴシゴシ洗うのではなく、お湯やたわしでサッと汚れを落とすのが基本です。洗剤を使うと油膜が剥がれてしまい、焦げつきやすくなる原因になります。調理後すぐにお湯で洗えば、汚れは意外と簡単に落ちます。どうしても油が気になる場合は、ごく少量の中性洗剤を使う程度にとどめましょう。
洗い終わったら、すぐに火にかけてしっかりと水分を飛ばすのがポイント。その後、キッチンペーパーでごく薄く油を塗っておくと、サビ防止にもなり、次回の調理も快適です。これらの手順を習慣にすることで、鉄フライパンはどんどん使いやすくなり、まるで“手になじむ道具”のように進化していきます。
トラブル対処法|サビ・焦げ付き・べたつきをリセット
どれだけ丁寧に扱っていても、サビや焦げ付き、ベタつきといったトラブルは起こり得ます。ですが、鉄製フライパンのいいところは、そんな状態になっても「リセット」できること。たとえば、サビが出た場合は金属たわしなどで削り取り、再度シーズニングをすれば問題なく復活します。
焦げ付きがひどい場合は、空焼きして炭化させてから削り落とし、油を塗って再生させる方法もあります。ベタつきが気になるときも、同様にリセットが可能です。これらのトラブル対応は一見難しそうに感じますが、慣れてしまえば簡単。まるでメンテナンスしながら長く乗る自転車のように、鉄フライパンとは“育てる付き合い方”ができる道具なのです。
使いこなしのポイントとちょっとしたコツ

予熱をしっかり、食材を入れるタイミングが大事
鉄製フライパンは「予熱が命」と言われるほど、調理前の加熱がとても重要です。まだ十分に温まっていない状態で食材を入れてしまうと、くっつきやすくなり、仕上がりが悪くなる原因になります。まずは中火〜強火で空焼きし、手をかざしてしっかり熱気を感じるくらいまで温めましょう。
目安としては、水滴を一滴落としたときに玉のように転がればOK。その後で油を入れて軽くなじませ、すぐに食材を入れることで、表面がカリッと焼き上がります。最初は難しく感じるかもしれませんが、温度管理に慣れれば、誰でもプロのような仕上がりが目指せます。
調理後は素早く盛り付けよう
鉄製フライパンは保温力が高いため、火を止めた後も熱がしばらく残ります。料理をそのまま置いておくと、余熱でどんどん火が通り、せっかくの絶妙な焼き加減が崩れてしまうことも。とくに卵料理や肉類などは、火の通しすぎを防ぐためにも、調理後すぐにお皿に移すのが鉄則です。
「まだ早いかな?」と感じるくらいで火を止め、すぐに盛り付けに移ることで、理想的な仕上がりがキープできます。また、調理後すぐに空の状態にしておくことで、焦げ付きや汚れも最小限に抑えられ、洗うのもラクになります。こうした一手間が、長く快適に使い続けるためのコツなのです。
洗剤・食洗機は避けて、サッと油を塗るだけ
鉄製フライパンは基本的に洗剤を使わずにお湯とたわしで洗うのがベストです。洗剤を使うと、せっかく育てた油膜が落ちてしまい、毎回“ゼロから”になってしまいます。また、食洗機にかけるとサビや変形の原因にもなるため、使用は避けましょう。ポイントは「調理後すぐ」に洗うこと。それだけで汚れの落ち方が大きく変わります。
洗ったあとは、火にかけて水気を完全に飛ばし、キッチンペーパーでごく薄く油を塗ることで、次回も快適に使える状態が保たれます。この“サッと油を塗る”というひと手間が、鉄フライパンの寿命を左右します。慣れてしまえば3分もかからないこの手順が、道具との良い関係を築く大切な習慣となります。
最後に
鉄製フライパンは、ただの調理器具ではありません。
手入れをしながら少しずつ馴染み、使うたびに性能が増していく――そんな“育てる道具”として、料理の時間に深みと愛着をもたらしてくれます。
もちろん、最初は少し手間に感じるかもしれません。ですが、正しい使い方とメンテナンスのコツさえ押さえれば、焦げ付きにくく、扱いやすいフライパンへと育ってくれます。そしてなにより、美味しく仕上がった料理を食べるたびに、「鉄でよかった」と感じる瞬間がきっと訪れるはずです。
もし「いつものフライパンに物足りなさを感じている」「もっと料理を楽しみたい」と思っているなら、鉄製フライパンは最良の選択肢のひとつ。あなたのキッチンにも、頼れる“一生モノ”の相棒を迎えてみてはいかがでしょうか。
追伸
Sorgeでは2025年8月下旬までクラウドファンディングを実施中です。
いち早く、最安値で無骨シェラパンを手に入れるチャンスです!
https://www.makuake.com/project/sierrapan/